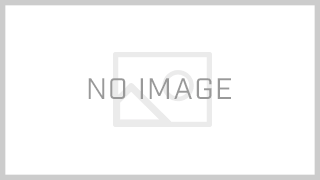■はじめに
電装DIYの定番といえば、ギボシ端子の取り付け。
配線をつなぐだけ──そう思って油断していました。
でも実際は、かしめ方ひとつで電気が流れたり止まったりするんですよね。
今回は、ギボシ端子を甘くかしめて通電不良を起こした実体験を紹介します。
■取り付けた直後は“ちゃんと動いていた”
LEDライトを追加したときのこと。
配線をギボシで接続し、点灯確認もOK。
「よし、完璧!」と満足してその日は終了。
ところが翌日、エンジンをかけてもライトがついたりつかなかったり。
叩いたら一瞬つくけど、すぐ消える。
最初はライトの故障を疑いましたが、原因は……ギボシのかしめ不良でした。
■原因:見た目はしっかりでも、内部はスカスカ
取り外して確認すると、端子は軽く抜けるレベル。
圧着ペンチで「軽く挟んだだけ」状態になっていました。
つまり、銅線がしっかり潰れておらず、導通が不安定だったんです。
加えて、
-
被覆の剥きすぎで芯線が短く、接触面が少なかった
-
圧着位置がずれており、外側のカバー側しか潰れていなかった
という初歩的ミスのダブルパンチ。
■DIYでの反省点
今回の失敗から学んだのはこの3つ。
-
圧着ペンチは必ず「ギボシ専用」を使う
→ 汎用のペンチでは、しっかり潰せません。 -
かしめたあとに軽く引っ張って確認する
→ 抜けなければ合格。動けばやり直し。 -
被覆の剥きすぎ・短すぎに注意
→ 芯線が見えるギリギリがベスト。
■修正と再接続
圧着をやり直してからは、ライトは安定して点灯。
導通テスターでも電気の流れを確認でき、**「やっぱり基本が大事」**と痛感しました。
ついでに周辺の配線も点検したところ、他にも甘い箇所を発見。
一度失敗すると、以降の作業が慎重になりますね。
■まとめ
ギボシ端子は小さな部品ですが、電気トラブルの原因になりやすい代表格。
「点灯した=大丈夫」ではなく、しっかり圧着しているかどうかを確認するのが大事です。
ギボシは“見た目より中身”。見えない接点こそ信頼性のカギ。