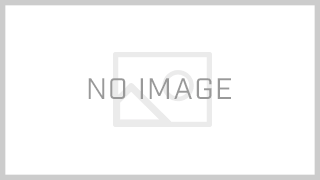電装DIYは「アース」で決まる!
電装品を取り付けるとき、ヒューズ電源や配線ばかりに気を取られがちですが、実は最重要なのが「アース」処理。
適当にボディに接続しただけでは電装品が動かない、誤作動する、最悪ショートするなど、トラブルの元になります。
この記事では、アースポイントの探し方と、失敗しない接続方法を実例付きで解説します!
アースとは?なぜ必要なのか?
-
電装品は「プラス電源(+)」と「マイナス(−)」で成り立っています。
-
車の場合、−極は車体(ボディ)に流す構造になっており、これを**「アース(接地)」**と呼びます。
-
つまり、電装品の−線をボディに接続する=アースを取るということ。
アースが不完全だと、通電しない・動作不良・誤作動・ノイズ混入などの問題が出るので、軽視は禁物です。
アースポイントの探し方
✅ 定番のアースポイント
-
ボディ鉄板にボルト固定されている金属部分
-
シートレールの固定ボルト
-
サイドステップ内のボルト穴
-
エンジンルーム内のフレーム接合部など
重要なのは「導通がある金属部であること」。鉄板であっても塗装や錆で絶縁されていればNGです。
🚫 アースにしてはいけない場所
-
内装パネルのクリップ穴や樹脂部品の上
-
塗装されたままの鉄板部
-
すでに複数の電装品が共締めされている場所
-
見た目が金属でも、実は中に絶縁樹脂があるボルト
💥 ありがちな失敗例(実話)
ボディ側は鉄板だし大丈夫だろうと、内張りの上から共締めしてアースを取ったんですが…
実はプラの内張りをボルトで挟んでいるだけだったようで、アース不良で電装品が一切動かず。
ボルトを外してみたら「下は樹脂、接地してなかった」ってオチでした💦
→ 「鉄板=アースOK」と思い込まず、内張りの素材や構造にも注意!
アース接続の正しい方法とコツ
🧼 1. 接触面は下処理が命
-
サビや塗装がある場合はサンドペーパーで研磨
-
接点復活剤やコンタクトスプレーで導通改善
-
汚れや水分もNG、きれいにしてから接続を
🔄 2. 丸型端子+ボルト固定が基本
-
接触面積が広く安定した導通が取れる
-
ギボシや剥き線は接触が不安定で不向き
-
ボルト+端子+ワッシャーでしっかり固定がおすすめ
⚠️ 3. 共締めの注意点
-
複数の電装品を同じボルトに共締めする場合は最大2系統までが安全
-
ワッシャーを挟んで端子がズレないようにする
-
締めすぎて端子がつぶれると逆に導通不良の原因に
アース不良の症状と対処法
-
スイッチONでも電装品が動かない
-
ランプが暗い・チラつく
-
リレーが動かない or 異音が出る
-
他の電装品と干渉して誤作動
✅ 確認方法:テスターで導通チェック
-
テスターの「抵抗モード(Ω)」でアース線とボディ間を測定
-
正常なら0Ω~数Ω程度
-
10Ω以上出るなら、接触不良 or 接地してない可能性大
まとめ|迷ったらテスター&確実な接地で!
アースは「見えないけど超重要」な配線処理です。
鉄板にボルト止めしたつもりでも、実は内張りや塗装が邪魔をして導通していないこともあります。
-
ボディにしっかり導通する場所を選ぶ
-
丸端子+サンドペーパーで下処理
-
共締めは構造と接点をよく確認する
トラブルの大半はアース不良。
「なんかおかしい」と思ったら、まずアースを疑いましょう!