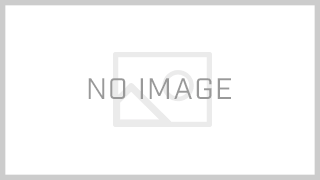🔧はじめに
電装DIYを始めると必ず出てくる「リレー」という部品。
なんとなく「スイッチの仲間かな?」と思っていても、実際の役割を正確に理解している人は意外と少ないです。
この記事では、リレーの基本構造と役割、使い方、接続のコツをわかりやすく紹介します。
初心者でも、この記事を読めば**「なぜリレーが必要なのか」**がしっかり理解できます。
⚡リレーとは?
リレーとは、小さな電気信号で大きな電流を制御するためのスイッチです。
簡単に言うと、「スイッチを押す代わりに電気でON・OFFする仕組み」。
たとえば、フォグランプやエアコンファンなど大電流が流れる装置を直接スイッチで制御すると、スイッチや配線が焼けてしまうことがあります。
そこで、リレーを間に入れて安全に電気を流す役割を果たすのです。
💡リレーの基本構造
一般的な自動車用リレーは「4極」または「5極」。
端子番号で見ると以下のような構成です👇
| 端子番号 | 役割 |
|---|---|
| 30 | バッテリー(電源)入力 |
| 85 | コイル(制御信号のマイナス側) |
| 86 | コイル(制御信号のプラス側) |
| 87 | 出力(ON時に電源が流れる) |
| 87a(5極の場合) | OFF時に通電する端子(通常は未使用) |
リレー内部では、85-86に電気を流すことでコイルが磁力を発生し、30-87の回路を接続する仕組みになっています。
🔋なぜリレーが必要なのか?
リレーを使う最大の目的は「電装品とスイッチを保護すること」。
たとえばフォグランプを直接スイッチで制御した場合:
-
電流が10Aを超えるとスイッチ接点が焼ける
-
長い配線を通すと電圧降下で明るさが落ちる
リレーを使えば、スイッチに流れるのは微弱電流(約0.1A)だけ。
ランプ側にはバッテリーから直接電気を供給できるため、明るさも安定し、スイッチ寿命も延びます。
🧰リレーの使い方(配線例)
【例】フォグランプを後付けしたい場合
1️⃣ 30番端子 → バッテリー+(ヒューズ経由)
2️⃣ 87番端子 → フォグランプへ
3️⃣ 85番端子 → スイッチ → ボディアース
4️⃣ 86番端子 → スイッチの電源側(ACCなど)
💡ポイント:ヒューズは電装品よりリレー側の近くに設置するのが安全。
⚠️リレーを使うときの注意点
-
定格電流(例:30A)を超える機器を接続しない
-
車両側のACC・IG電源の取り出し位置を間違えない
-
防水リレーを使うと雨天時のトラブル防止になる
-
配線の被覆剥きすぎに注意!ショートの原因になります
参考記事:
👉 ヒューズボックスから電源を取るときの注意点
👉 電源の取り方を間違えるとショートする?安全な配線分岐方法
🔗おすすめの防水リレー・DIYパーツ
✅まとめ
| 内容 | ポイント |
|---|---|
| リレーの役割 | 小さな電流で大きな電流を安全に制御する |
| メリット | スイッチや配線の保護、電圧降下の防止 |
| 使い方のコツ | 30→電源、87→出力、85/86→制御回路 |
リレーは一見難しそうに見えますが、構造を理解すればシンプルな仕組みです。
電装DIYを安全に楽しむためにも、ぜひリレーの正しい使い方を覚えておきましょう!